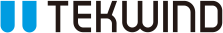一元的に管理するだけではない?タブレットを漁業にも活用できる
- 2023.01.13
- 業種別活用法

ビジネスのICT化・スマート化は、漁業分野にも広がっています。養殖業においては早くから生産管理にICTが活用されてきましたが、近年では沿岸漁業でもシステムの開発が進められています。
そのシステムに役立つのがタブレットです。この記事では、水産分野におけるデータ管理や漁業ならではの使い方を事例で紹介します。また、急速に整備化が行われているスマート漁業と今後の展開などについても解説します。
漁業の現状とタブレットのメリット
近年、漁業分野は廃業が増加の傾向にあり、危機的状況を打開する手段としてテクノロジーの活用が進められています。これまで経験や勘に頼っていた海況、漁場などをデータ化・分析することで不規則であった水揚げ量を予測できるようになるほか、効率的な漁や事業継承、新たなビジネスモデル開発の可能性が期待されています。
その中で特に沿岸漁業、定置網業でのタブレット活用が開始されるようになりました。船上や漁場など現場での作業においては、タブレットの携帯性が大きなメリットと言えます。船上は漁に使う道具や機器を搭載していおり、その中でタブレットはコンパクトに持ち運ぶことができて置く場所にスペースをとりません。
また現場作業がメインの仕事では、視認性・操作性に優れている点も最適と言えるでしょう。漁場でさまざまな数値や地図を見ることもあるため、拡大・縮小などタップしながら操作・確認しながら作業をすることができます。
漁業ならではの使い方
それでは、実際の現場でタブレットをどのように活用しているのでしょうか。事例をいくつか紹介します。
デジタル操業日誌
タブレットを活用する事例として、操業日誌の入力があげられます。これまで各漁業組合では、漁業者が紙に記入していた操業日誌を月単位で回収・コピー・システムへの入力など、保管までに多くの時間を必要としていました。
タブレットを活用することにより、漁獲情報・位置情報・水温・日時などすべて電子データとして送信するだけでデータベース化、組合側はエラーチェックのみの作業となります。
データ保管までの工数を大幅に削減するほか、記録と保管、漁業者との情報共有もできるようになっています。
海況状況予測・漁場予測
漁業は、気候や海水温、環境の変化などさまざまな条件により漁獲できる魚の種類や漁獲量が不規則になりがちです。そこで、魚を集めるため人工的につくられている浮魚礁(うきぎょしょう)に水温や流速を計測できる機器を取りつけ、海況を観測できるシステムを構築しています。
また、海水温観測データと過去の漁獲記録を解析し、漁場を予測するシステムなども開発されています。漁業者がリアルタイムに漁場予測を確認できるため、漁業の効率化・漁船にかかる燃費の削減などにつながっています。
定置網では、海中にカメラを設置し漁業者がタブレットやスマホを使って画像データを確認しながら漁獲に活用しています。
資源回復・保護活動
データをデジタル化することにより、資源の回復にも役立てています。北海道留萌市では、乱獲によりナマコの数が減少してしまったことから、漁業者の記録をもとに資源量の分析・予測を行うシステムを構築しました。
このシステムによって漁業者に資源量を認識してもらうことができるようになり、ナマコの資源量は2010年の59トンから2015年には96トンと回復に向かっています。
北海道ではほかにもウニ・アワビなどの漁獲量の調整を行っているほか、位置情報や流速情報をもとに海難救助の体制づくりにも取り組んでいます。
スマート漁業と水産の未来
水産庁をはじめ都道府県や漁業組合、また関連する企業が「スマート漁業」の取り組みを推進しています。海洋データや漁獲量、資源量などさまざまなデータを活用して、魚種ごとの予測システムや新しい流通システムの構築が行われています。
たとえば、位置情報、漁獲情報をリアルタイムで共有することで、漁港では氷やトラック、出荷の準備などをスムーズに行えるようになります。
また、漁獲予測システムと連動した予約販売促進システムをつくり、漁業者と観光物産やレストランなどの直接取引が可能になる仕組みを検討しているほか、店舗では限定企画の開催、オンラインショップでの購入など、新たなビジネスや顧客体験が期待されます。
ほかにも、蓄積されたデータから事業継承や新しい教育システムに生かす取り組みなども行われています。
まとめ
漁業者がタブレットを活用しシステム化することで、不法漁業をなくし魚の価値向上や健全な流通も可能になるでしょう。
現時点では、海上でのシステム故障時の対応策、漁業者のタブレット操作スキルの向上など課題もありますが、将来的にはスマート漁業の普及でタブレット活用が増加すると考えられています。
漁業用タブレットは、防水性能の高いものを選ぶことも重要なポイントです。
テックウインドでは、用途に合わせたさまざまな機能のタブレットを取り揃えています。