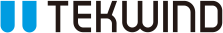授業はICT化の時代!学校でのタブレットの活用事例と課題は?

文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、多くの小学校や中学校では一人の児童・生徒が一台のタブレットを使って授業を行うようになりました。
学習にタブレットを利用することで、先生は授業でわかりやすく説明できるようになり、児童や生徒は授業の理解度が高まっています。
しかし、タブレットを利用した授業が始まってから間もないこともあり、タブレットをどのように活用すれば良いか、タブレット学習を行ううえでの課題をどのように解決すれば良いか、という悩みを抱えている学校もあるのではないでしょうか。
この記事では、学校でタブレットを活用する場合の事例と課題について説明します。タブレット学習に関する理解を深め、授業においてタブレットを有効に活用しましょう。
目次
学校でタブレットはどの程度普及している?
学校教育におけるタブレットの普及率について、文部科学省が2021年に実施した調査結果「端末利活用状況等の実態調査(令和3年7月末時点)(速報値)」を参照します。
それによると、小学校等、中学校等で端末を全学年で利活用している、一部の学年で利活用している、という二つの回答を合わせると下記の結果となりました。
小学校等:96.1%
中学校等:96.5%
また、全国の自治体における端末の整備状況についてみてみると、96.1%の自治体で整備が完了しており、整備が済んでいない自治体は3.9%にとどまりました。
なお、端末の整備が完了した状態とは、児童と生徒に端末が行き渡っていること、学校においてインターネットが整備されている状態で、タブレット学習が可能になっている状態を指します。
出典:文部科学省 端末利活用状況等の実態調査(令和3年7月末時点)(速報値)
https://www.mext.go.jp/
2019年に政府が打ち出した「GIGAスクール構想」では、日本の教育におけるICT化の実現を掲げており、全ての児童と生徒がタブレットを利用して教育を受けることを目的としました。
2020年以降は新型コロナの感染拡大により、日常生活のあらゆる場面においてICT化が進みましたが、その流れは学校においても同様に進んでいます。
上記の調査結果にもある通り、小学校・中学校におけるタブレットの普及率は高く、タブレットを利用した学習は日常的に行われるようになりました。
学校教育におけるタブレットの活用事例
学校教育におけるタブレットの活用事例としては、下記があげられます。
・授業の資料として、画像や動画を活用できる
・児童・生徒同士で、問題の答えについて意見を交換し合える
・宿題をタブレットで提出できる
授業の資料として、画像や動画を活用できる
授業中にタブレットを利用すると、授業の資料として画像や動画を活用できます。
従来は、授業に関する資料はプリントにまとめておき、それを配布して説明することが一般的でした。しかし、タブレットを利用することによって、さまざまな画像をタブレットに表示できるようになったほか、動画を活用して授業の内容を説明することも可能となりました。
タブレットを利用することで、授業をわかりやすく説明できます。
児童・生徒同士で、問題の答えについて意見を交換し合える
タブレット学習をすると、ある問題の答えについて、児童や生徒同士で意見を交換し合うことができます。
例えば、国語の時間に物語の内容を教科書で読んだとき「主人公がとった行動について、あなたはどう思いますか?」という質問を投げかけたとしましょう。
児童や生徒がタブレットの画面上で答えた内容は、お互いに内容を確認できるため、児童や生徒の間で、お互いにフィードバックし合うこともできます。
タブレット学習を行うと、児童や生徒はタブレットを通じて自分の意見を表現しやすくなります。一つの出来事に対して、さまざまな観点から意見を交わし合えるのも、タブレット学習ならではといえるでしょう。
宿題をタブレットで提出できる
タブレット学習なら、宿題をタブレットで提出できます。
タブレットの画面に宿題の内容が表示されたら、タブレットの画面上で宿題を行います。宿題が終わったら送信するだけで先生に提出できます。
従来は、宿題は紙で提出することが一般的であったため、児童や生徒は宿題のプリントを提出するまではなくさずに保管しておく必要がありました。
さらに、先生は児童や生徒から集めた宿題をまとめておく必要があり、保管しておく手間がかかる点がネックとなっていました。
タブレットなら宿題が全て電子データとしてまとめられているため、児童や生徒は宿題を簡単に提出でき、先生は宿題のデータをタブレットでチェックするだけで済むので、宿題の提出や管理の手間がかかりません。
タブレット学習における課題
小学校や中学校においてはタブレット学習が日常的に行われており、教科書など紙媒体の教材を利用した学習と比べると学習効果の向上が期待されます。
一方で、タブレット学習においては課題もあり、学習効果をより一層高めるためには、課題の解決が必要となります。
タブレット学習における課題としては、下記があげられます。
・通信環境の整備
・セキュリティ面の課題
・破損や紛失した場合の対応
通信環境の整備
タブレット学習を支障なく行えるようにするには、通信環境の整備が必須となります。
現在では、ほとんどの小学校や中学校で児童・生徒一人一人がタブレットを利用して学習を行うため、授業中には全校の児童・生徒数百人が一斉にタブレットで通信します。
タブレットを使い、動画で説明しながら授業することも想定すると、大容量通信に耐えうる高速のインターネット環境の整備が必要です。
タブレットを活用した授業においては、児童・生徒一人一人にタブレットを支給するという面が重視されますが、質の高い授業を行うためには通信環境の整備も重要となります。
セキュリティ面の課題
タブレットを利用するうえで注意したい点はセキュリティの問題です。特に、学校では多くの児童・生徒がタブレットを利用するため、タブレットを利用する際のセキュリティ面について十分に教育しておく必要があります。
タブレットのセキュリティ対策は、タブレットを利用するときに一定のルールを設けることです。そして、そのルールを児童・生徒に守ってもらいます。
タブレットを利用するときに理解しておきたい点は、あくまでも学校のタブレットであり、個人のタブレットではない、ということを十分に認識することが重要となります。
タブレットを利用するときのルールとしては、下記があげられます。
・他人のタブレットを勝手に利用しない
・授業が終わったら、タブレットは元の場所に戻す
・学習で必要なサイト以外は閲覧しないようにする
・学校内の写真、児童・生徒が映った画像をネット上にアップしない
これらを児童・生徒に守らせることにより、個人情報の流出を抑えられるほか、サイトを閲覧したことによるトラブルの予防にもつなげられます。
それに加え、学校側でもタブレットを利用したときに起こりうるトラブルを防ぐ対策を講じておく必要があります。主な対策としては下記があげられます。
・児童や生徒にとって不適切なサイトが表示されない設定にする
・画像など個人情報が含まれるファイルを学校外の人と共有できないようにする
・タブレットを紛失したとき、第三者の利用を防ぐためにロックする
これらの対策を講じることにより、個人情報の流出やサイト閲覧時のトラブルを防げるほか、タブレットを紛失したときの不正利用も防げます。
破損や紛失した場合の対応
全ての児童・生徒がタブレットを利用して学習できるようになることはメリットといえますが、そこで問題となりやすいのはタブレットを破損したり、あるいは紛失したりする可能性が高まることです。
そのため、タブレットを破損・紛失した場合にどのような対応が必要か、という点が課題となります。
その場合の対応方法として、文部科学省が実施した調査結果「端末利活用状況等の実態調査(令和3年7月末時点)(速報値)」を参照します。
同調査によると、破損・紛失した場合の対応は下記の通りとなりました。
・事業者との保守契約等により代替機などを手配:27.6%
・予備機を活用:72.0%
・その他:0.4%
出典:文部科学省 端末利活用状況等の実態調査(令和3年7月末時点)(速報値)
https://www.mext.go.jp/
上記の調査結果によると、破損・紛失した場合の対応方法は、予備機の活用が最も多く、代替機の手配は3割程度にとどまりました。
児童や生徒が授業でタブレットを利用することを踏まえれば、代替機の手配が最適といえますが、予備機で対応するケースが多いことを理解しておくと良いでしょう。
まとめ
コロナ禍に機にあらゆる場面でICTの導入が進んでおり、学校においても「タブレット学習」という形でICT化が進んでいます。
タブレットを導入することによって、画像や動画を授業の資料として活用できるため、先生としてはわかりやすく授業を教えやすくなったほか、児童や生徒の立場としては授業を理解しやすくなりました。
なお、タブレット学習を円滑に行うためには、通信環境の整備が必須となります。全校生徒が一斉にタブレットを利用する状況においては、大容量通信が可能な環境が求められます。
そのほか、タブレットを利用する際にはセキュリティ面の対策を講じる必要があります。学校側で閲覧できるサイトを制限したり、外部へのファイル送信を制限したりするなどの対策が必要であるほか、タブレットを利用する際には一定のルールを設けることも必要でしょう。
タブレットを活用した授業はスタートしてから日が浅く、さまざまな課題に直面する場合もありますが、課題の解決方法を理解して、タブレット学習を効果的に行いましょう。