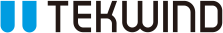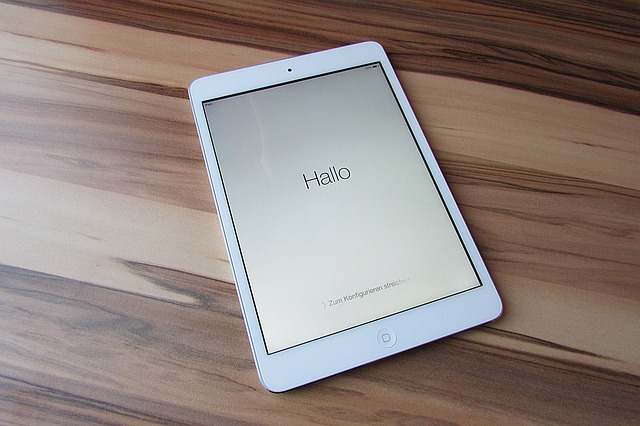タブレットやPCでも要注意!タブレットでもなるスマートフォン症候群とは
- 2023.04.02
- その他

近年、スマホやタブレットがビジネスでもプライベートでも使われるようになりましたが、日常的に使う頻度が増えたことで「スマートフォン症候群」のリスクも高まっています。
スマートフォン症候群は、スマホだけでなくタブレットでも同様の症状が起きる可能性があります。
本記事では、スマートフォン症候群がもたらす身体への影響を説明します。また、スマホやタブレットへの依存度をチェックしながら、心身の健康のためにどのような対策をとるべきか考えていきましょう。
スマートフォン症候群のもたらす症状
スマートフォン症候群は、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを長時間使用することにより引き起こされる健康障害です。どのようなものがあるか見ていきましょう。
ストレートネック
ストレートネックとは、本来緩やかにS字にカーブしているはずの首の骨(頸椎)が、下を向いた姿勢を継続することにより骨がまっすぐになってしまう状態をいいます。
うつむいた姿勢は頭部の重心が前に傾くため、首や背中に負担がかかり肩こりや腰痛を引き起こします。筋肉の弱い女性に多いといわれている症状です。
猫背・巻き肩
画面を見ることで身体が前屈みの状態になり、背中が丸まって猫背になったり、両肩が本来の位置よりも内側に傾く巻き肩になったりします。特に座り姿勢でタブレット画面を見るときに注意が必要です。
姿勢が悪くなることで見た目にも影響しますが、肩こりや腰痛をはじめ、冷えや便秘などの原因にもなります。
眼精疲労・ドライアイ
スマホやタブレットの画面を長時間見ていると、目のピント調整機能が低下して目が疲れやすくなります。また、画面を見ている間は瞬きの回数が減るためドライアイになり、目の痛みや不快感といった症状につながることもあります。
うつ病
タブレット画面でうつむいた状態が続くと、首の神経を圧迫し副交感神経の働きが低下します。頭痛やめまい、腹痛などを引き起こすほか、自律神経が乱れて疲れやだるさ、不眠などに陥ることがあり、長期化するとうつ病にまで発展する可能性があります。
注意しよう!スマホ・タブレットの依存度チェック
スマートフォン症候群は、スマホやタブレットなどの端末を使っていないと気が済まない、落ち着かないなど依存してしまっている状態です。
依存度が高くなると、健康によくないと分かっていてもコントロールできなくなってしまいます。次のような行動は依存する傾向があるのでチェックしてみてください。
・食事中やお風呂にも端末を持ち込んでいる
・就寝前にも端末を見ている
・起床するとはじめにスマホやタブレットをチェックする
・常にLINEやメールをチェックし、返信が来ないとイライラいする
・常に端末が手元にないと不安になる
・外出中に充電が切れると不安になる
スマホやタブレットに依存することは病気ではありませんが、使い続けることによる健康被害へのリスクが高くなります。特に年齢を重ねるにつれ、副交感神経の働きは低下するため、心身が不安定になることも考えられます。
スマートフォン症候群にならないための対策
では、スマートフォン症候群にならないためにはどうしたらよいでしょうか。いくつか考えられる対策をあげてみましょう。
常に姿勢を意識する
画面を見て集中していると姿勢を忘れがちです。特に座り姿勢だと、タブレットをテーブルなどに置いてかがむ姿勢になるため、猫背や巻き肩になる可能性が高くなります。
座ってタブレットを使用するときは、骨盤を立てて座り、猫背にならないよう意識しましょう。タブレットスタンドを使って高さを調節するのも1つの方法です。
立って使用するときは、タブレットを胸に近づけるのではなく、身体から少し離し高い位置になるようにします。作業にはタッチペンを使うのもよいでしょう。
30分に1回は目を離す
30分に1回は、画面から目を離して休憩をとりましょう。画面に釘付けになると筋肉が硬くなったり、ドライアイになったりします。目がかすむ、疲れると感じる場合は遠くを見るようにするか目を冷やすのも効果的です。
ストレッチをする
目が疲れたときは目の周辺をマッサージし、首や肩が凝ったときはストレッチを行いましょう。首を前後左右にゆっくりと伸ばす、首を回す、手を後ろに組んで胸を開くようにするなど、無理なくできるものを取り入れます。前屈みの姿勢を続けないことが大切です。
寝る前は使用しない
タブレットは動画なども見やすいですが、夜遅くまで見ていると寝不足になり、継続すると疲れやすくなります。使用する時間を決め、生活リズムを崩さない使い方を考えましょう。
まとめ
タブレットはどこにでも持ち込めるため便利ですが、長時間使うと疲れやすくなります。仕事の効率を上げるために使用している端末も、疲労でかえって生産性が低下し仕事のミスにつながる可能性もあります。
適度な利用を心がけて仕事の支障にならないようにしましょう。
テックウインドでは、タブレットのさまざまな使い方を提案しています。
タブレットの導入を検討していたり、課題を抱えていたりする企業様はタブレットの豊富な支援実績を持つテックウインドにご相談ください。