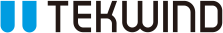主要な駅で活用されているタブレット どんな業務に利用されている?

利用客の多い駅では、駅員は利用客から頻繁に問い合わせを受けており、その対応に追われます。また、構内が広い駅では他の駅員と連絡を取る機会も増えます。
駅員が効率的に業務を行えるようにするために、主要な駅ではタブレットが広く導入されています。
駅はどのような業務においてタブレットを活用しているのか、また、駅でタブレットを導入することでどんなメリットがあるのか、という点について説明します。
目次
駅でのタブレット活用事例
駅でのタブレット活用事例としては、下記があげられます。
・駅構内の案内
・路線の乗り換え情報を簡単に案内
・翻訳や筆談の機能で駅利用者とコミュニケーション
・駅員同士で情報共有
・業務マニュアルを電子化
それぞれの活用事例について説明します。
駅構内の案内
駅構内の案内をタブレットで行うと、駅の利用者にとってはわかりやすく感じられます。
例えば、駅の利用者がコインロッカーを探しているとしましょう。駅員にコインロッカーの場所を訪ねた場合、駅員はタブレットの画面に駅構内の案内図を表示させてコインロッカーの場所を指し示すことができます。
駅の利用者にとって利用しやすい駅であるためにも、タブレットでの案内は必須といえるでしょう。
路線の乗り換え情報を簡単に案内
タブレットを利用すれば、路線の乗り換え情報を簡単に案内できます。
東京や大阪など、大都市には多くの路線があるため、目的地に行くためにはどの路線を利用すれば良いのかがわかりにくく感じてしまいます。
現在では、スマホを利用して乗り換えの方法を自分で調べることもできますが、乗り換えの方法が複雑でわかりにくいと感じた場合は、駅員に聞くとよりくわしく教えてもらえます。
駅員は、タブレットの画面に乗り継ぎについての方法を表示させて、駅の利用者にわかりやすく説明できます。
画面に表示した内容を活用しながら説明できれば、駅の利用者としてはわかりやすいと感じられることでしょう。
翻訳や筆談の機能で駅利用者とコミュニケーション
タブレットに翻訳や筆談のアプリがインストールされていると、駅の利用者とコミュニケーションを取りやすくなります。
駅では外国人の利用者から問い合わせを受けることもあります。タブレットで翻訳機能が利用できれば、翻訳の画面に日本語を入力すると、入力した内容は指定された外国語で表示されます。
例えば「甲州街道改札は、ここからまっすぐ進んだ所にあります」と入力すれば「The Koshu-kaido gate is straight ahead from here.」と翻訳されるので、外国人にとってもわかりやすいと感じます。
また、駅は耳が不自由な人も利用することがあります。耳が不自由な人に案内する場合に備えて、タブレットに筆談のアプリをインストールしておくこともできます。
利用者も駅員も文字を使いながらコミュニケーションを取れるので、駅員が伝えたいことはタブレットの画面を介して利用者に伝えられます。
駅員同士で情報共有
全ての駅員にタブレットが行き渡れば、駅員同士での情報共有も簡単に行えます。
例えば、列車の運行に遅れが生じたため、今後の列車の発車時刻を変更する場合、変更後の発車時刻はタブレットに一斉送信できます。
これにより、列車の運行状況を指令する運転指令所で決めた内容は即座にタブレットに反映されるため、列車に遅れが生じた場合であってもスムーズな対応が可能となります。そのため、列車の乗客に不便をかけずに列車を運行できます。
業務マニュアルを電子化
タブレットを利用すれば、業務マニュアルを電子化できます。
鉄道事業者のマニュアルは種類が多いうえに、紙媒体のマニュアルはいずれも厚くなるため、マニュアルの持ち運びはかさばるうえに重い点がデメリットでした。
業務で使用するマニュアルをタブレットで閲覧できるようにすれば、マニュアルの内容がどんなに多くなっても、紙媒体のように重くなることがありません。
しかも、タブレットなら探したいマニュアルを簡単に検索できます。紙媒体のようにマニュアルを探すのに時間がかからないため、業務が効率化します。
駅での業務をタブレットで行うメリット
駅での業務をタブレットで行うメリットは、下記があげられます。
・駅の利用者にとって利便性が向上する
・駅員の業務が効率化する
・駅員の間で、列車の遅れなどの重要な情報を共有できる
それぞれについて説明します。
駅の利用者にとって利便性が向上する
駅の業務でタブレットを利用すると、駅の利用者にとっても利便性が向上します。
例として、駅の利用者が駅員に乗り継ぎの方法などを問い合わせるとしましょう。駅員が言葉で説明しようとすると、駅の利用者に対して伝わりにくくなってしまいます。
しかし、タブレットに乗り換え案内の画面を表示できれば、駅員は画面を使いながら駅の利用者に説明できるので、駅の利用者としてはわかりやすいと感じられます。
駅員の業務が効率化する
タブレットを利用することで、駅員の業務が効率化します。
複数の業務マニュアルが電子化されるため、業務中に紙媒体のマニュアルを持ち歩く必要がなくなるほか、タブレットの通話機能を利用すると、駅構内の離れた場所にいる他の駅員と簡単に連絡が取れます。
さらに、他の駅員と連絡を取る際に、駅構内の画像も添付できるので、自分がいる場所の状況をくわしく説明できます。
業務を効率化して働きやすい環境づくりを目指すなら、タブレットの導入は必須といえるでしょう。
駅員の間で、列車の遅れなどの重要な情報を共有できる
業務にタブレットを導入すると、駅員の間で列車の遅れなどの重要な情報を共有できます。
列車が遅れてしまうと、列車の乗客に迷惑をかけてしまうため、遅れに関する情報は迅速に伝える必要があります。
タブレットが導入される前は、列車の遅れに関する情報は運転司令室からの連絡を待たなければならなかったため、列車の遅れの情報を迅速に伝えることが、難しい状況でした。
タブレットの機能を利用すると、どの区間でトラブルが発生しているのか、この列車は何分ほど遅れるか、という情報を一目で確認できます。
これにより、列車の乗客に対して、列車が遅れている原因、列車が発車するのはいつ頃になりそうか、終着駅に到着するのは何時頃になりそうか、という情報をスピーディーに伝えられます。
このように、駅員同士で重要な情報を共有できることにより、乗客への案内を適切に行えます。
まとめ
駅構内において、タブレットは駅利用者に対する案内業務、駅利用者と駅員または駅員同士のコミュニケーションツールとして活用されています。
さらに、タブレットを導入することで各種マニュアルが電子化されるため、持ち運びが便利になるだけでなく、調べたいマニュアルの検索も簡単に行えるようになります。
駅での業務用としてタブレットを導入すると、駅員の業務が効率化するほか、駅の利用者は駅員からわかりやすい説明を受けられるため利便性が高まります。
タブレットは多くの機能を利用できるうえに、持ち運びしやすいサイズであるため、駅での利用に適しています。駅利用者の満足度を高め、駅員にとって働きやすい環境をつくるためにも、タブレットの導入を検討してみましょう。
様々な情報を表示するデジタルサイネージの活用方法についてさらに知りたい方は、下記のページを参考にしてみてください。